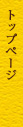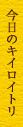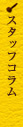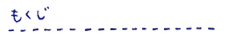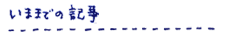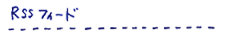「寺門広気」+「つむぎや」
カテゴリ :
つむぎや

今年最後の展示は、寺門広気さん。
12月7日(金)から始まります。
その展示に合わせて、12月8日(土)には
黄色い鳥器店3階に「つむぎや」が
1日限定で料理店をオープンします。
※詳しくはこちらをご覧ください。→ ☆
先日、その打ち合わせに
「つむぎや」のマツーラさんと金子さんと
寺門さんの工房へうかがいました。
寺門さんの器に「つむぎや」の料理を盛りつけ、
手巻きごはんをみんなで愉しくいただきます。
まずは、今日の料理の説明を。

寺門さんの器、いろんな絵が描かれていますが
お料理が映えます。

工房へもお邪魔しました。

素焼きを終えて絵を描かれるのを待つ器。
どんな絵が描かれるのでしょうか?

人気の小皿。たくさん焼き上がっていました。

工房での寺門広気さんと「つむぎや」のおふたり。

「にやり。」

「にやり、にやり。」

高知 仕入れの旅
カテゴリ :
仕入れの旅
前回のつづきです。
小坂明さんのところにうかがった翌日
工房を見せていただきました。
小坂さんのめし碗を削る作業を
撮影させてもらいました。
ご覧ください。

前の日にロクロで挽いためし碗
お手製の道具で仕上がりの高さを測ります。

先ず、側面を鉋を使って削ります。
少し柔らかいかなと思える状態で削ります。

そして、高台の内側。

均一になったか手で調べます。


均一になるようにさらに削ります。
流れるような作業で見ていてうっとりします。
削り終えたら、
拭き漆で仕上げるためのベース作り。
表面を磨きます。

最初は、水牛の角で出来たヘラで。

次にスプーンの裏を使って全面をつるつるにします。
内側も、磨きます。

金属のスプーンをつかって丁寧に。
出来上がったら、棚板に載せて乾かします。

この器をサヤに入れて炭化焼成した後に、
漆を塗って低温で焼き付けたものが
黄色い鳥器店でも人気の「拭き漆」の器です。

焼き上がるとこんな感じのめし碗になります。
手に吸い付くような感触には、
ちょっとビックリさせられます。
このめし碗で食べるとごはんがとっても
おいしく感じます。
工房にはお手製の美しい道具がたくさん。

工房からの眺め。窓の外は緑がいっぱいでした。

高知 仕入れの旅
カテゴリ :
仕入れの旅
11月9日(金)から始まる小坂明さんの器展。
そのうち合わせにこの夏、小坂明さんの工房を訪ねました。
高知空港で車を借り、先ず桂浜でこの方にご挨拶を

した後、小坂さんの工房のある須崎市へ向かいます。
小坂さんのご自宅兼工房は、須崎の小さな半島の上にあります。

リビングからの眺めは帰りたくなくなるほど。

小坂さんの器でいただく枝豆。
器も目に美味しかったです。

高知名物「チャンバラ貝」。

器は最後の調味料と言います。いい器です。

工房に初めてうかがって
小坂さんの器を見たとき、
ちょっと地味過ぎるかなと思いました。
それと黄色い鳥器店で扱うには
少し高級かもしれないと..。
そんな時、「食器棚にはいろんな作家の器があるけれど、
なぜか手にしてしまうのは小坂さんの器。
ほんとうに使いやすい器を作られるおススメの作家よ。」
と、小坂さんをご紹介してくださったギャラリーSUMIさんの
言葉を思い出して、とりあえず自分用に急須と湯呑みをいただいて帰ってきました。
あの時からわが家の食卓では小坂さんの器が
大活躍していいます。個展に通い
拭き漆のめし碗、長湯呑み、粉引きの中鉢
いろんな器を買い揃えました。
使う度にいい器だなーと実感させられます。
使いやすいということにこだわった時代に
流されない器ってこういうものなんだなと実感します。
SUMIさんに感謝です。
高知の美味しいものをいただいた後、
大きな楠があるご近所の神社へも案内していただきました。

この大楠の木が、小坂さん家族がこの土地に住む
きっかけのひとつになったそうです。
続きは、また明日。
工房での小坂さんの制作風景をご紹介します。
お楽しみに。